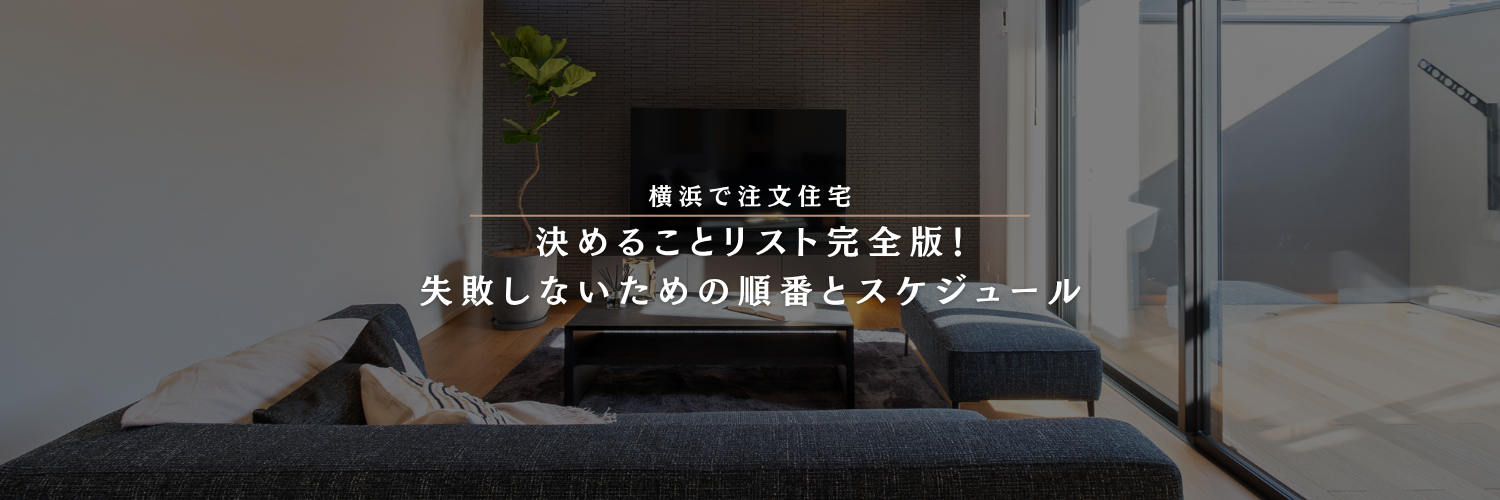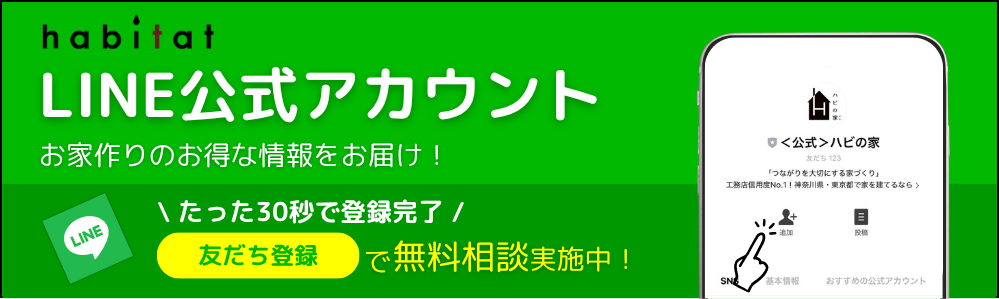横浜で注文住宅を建てようと決めたとき、その自由度の高さに胸が膨らむ一方で、「一体、何から決めることになるんだろう?」「決めることが多すぎてパニックになりそう」という不安を感じていませんか?
家づくりは、人生で最も大きなプロジェクトの一つです。そして、その成功の鍵は「決めること」の順番と流れを正確に把握し、優先順位をつけることにあります。
この記事は、横浜・神奈川エリアで多くの注文住宅を手掛けてきた私たちが、注文住宅で決めることの全体像を「やることリスト」として時系列で徹底解説する完全版ガイドです。
失敗しない、後悔しない家づくりのために、まずはこのリストとスケジュールで全体像を掴みましょう。
注文住宅は「決めること」が多すぎる!まずは全体像を把握しよう

なぜ注文住宅は「決めること」がこんなにも多いのでしょうか? それは、建売住宅とは異なり、土地の選定から間取り、壁紙の色、コンセントの位置一つひとつまで、すべてをゼロからご家族の理想に合わせてオーダーメイドできる「自由度の高さ」の裏返しだからです。
しかし、その膨大な選択肢を前に圧倒されてしまうと、打ち合わせがストレスになったり、重要な判断を誤ったりする原因にもなりかねません。
失敗しない家づくりの第一歩は、闇雲に詳細から決めるのではなく、家づくり全体の流れ(スケジュール)と、どのタイミングで何を決める必要があるのか、その全体像を把握することです。
家づくり全体の流れと「決めること」のタイミング
注文住宅のプロジェクトは、一般的に以下のような流れで進みます。それぞれのフェーズで「決めることの質」が異なります。
- 構想・予算決めフェーズ(検討開始〜約1ヶ月)
- 決めること:家づくりの「軸」となる最も重要な方針。
- 土地・会社選びフェーズ(約2〜6ヶ月)
- 決めること:家づくりの「土台」となる土地と、理想を形にするパートナー。
- 設計・打ち合わせフェーズ(約3〜6ヶ月)
- 決めること:家の「すべて」を決める、最も密度の濃い期間。
- 着工・完成フェーズ(約4〜6ヶ月)
- 決めること:建築中の確認と、建物「以外」の最終仕上げ。
このスケジュール感を頭に入れながら、次の章で具体的な「決めることリスト」を時系列で見ていきましょう。
【時系列】注文住宅で決めることリストと流れ
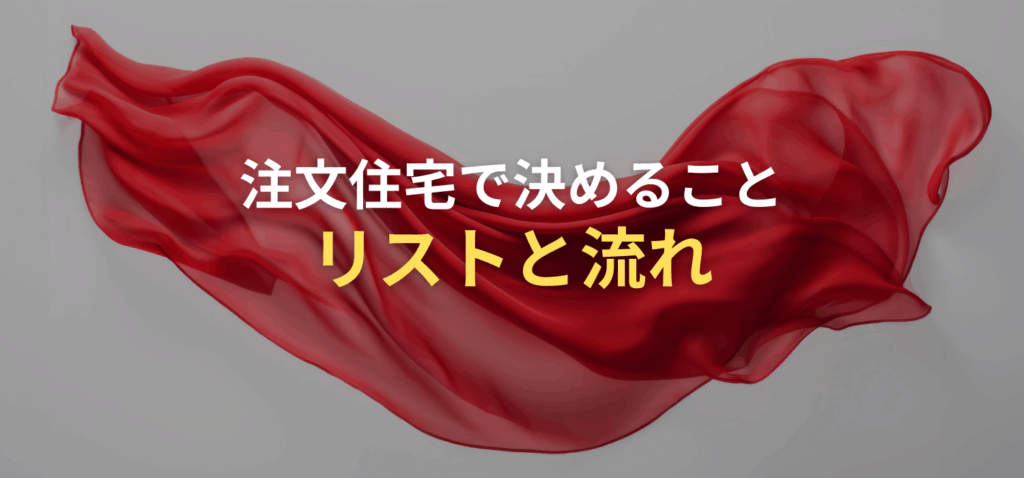
家づくりの4つのフェーズごとに、「決めること」と「やること」をリスト化しました。
2-1. 構想・予算決めフェーズ(検討開始〜約1ヶ月)
家づくりのスタート地点です。ここで決める「軸」がブレると、後々の打ち合わせで迷走してしまいます。
- 予算・総費用の決定
- 注文住宅にかかる総費用(土地代+建物本体工事費+諸費用)の全体像を把握します。
- 自己資金はいくら出すか、住宅ローンはいくら借りるかを仮決めします。
- Point:諸費用(登記費用、ローン手数料、税金など)は総費用の10%前後かかると見込んでおくのが、失敗しないコツです。
- 家づくりのテーマ・コンセプト(どんな暮らしがしたいか)
- 「家族が集まる開放的なリビングが欲しい」「趣味のガレージが最優先」「家事動線が楽な家にしたい」など、新しい家で実現したい暮らしのイメージを固めます。
- Point:「なぜ家を建てるのか?」という根本的な動機を家族で共有することが、優先順位付けの基準になります。
- 希望エリアの決定
- 横浜市のどの区か(例:青葉区、港北区、戸塚区など)、どの沿線(例:東横線、田園都市線、ブルーライン)が良いか。
- 通勤・通学の利便性、周辺環境(商業施設、公園、治安)など、エリアに求める条件を整理します。
2-2. 土地・会社選びフェーズ(約2〜6ヶ月)
構想が固まったら、それを実現するための「土地」と「パートナー」を決めます。
- 依頼先(建築会社)の選定
- ハウスメーカー、工務店、設計事務所のどれに依頼するかを決めます。
- Point:横浜・神奈川エリアで、自分たちの理想とするデザインや性能(耐震・断熱)の実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。「横浜市 工務店 選び方」などで検索し、施工事例をよく比較検討しましょう。
- ハビタットのような地域密着型の工務店は、地域の特性を理解した柔軟な設計提案を得意としています。
- 土地探しと決定
- 希望エリアの不動産情報を収集します。
- 建築会社に土地探しをサポートしてもらうか、不動産会社を介して探します。
- Point:土地を決定する前に、必ず建築のプロ(依頼予定の工務店など)に「法規制」「地盤」「日当たり」などをチェックしてもらうことが、後悔しないための絶対条件です。
2-3. 設計・打ち合わせフェーズ(最重要・約3〜6ヶ月)
家づくりの「花形」であり、最も「決めること」が多い最重要フェーズです。打ち合わせは週に1回、2〜3時間程度行われることが多く、内容も多岐にわたります。
- 間取り(ゾーニング、部屋数、動線)
- LDKの広さ、部屋数、収納の場所と広さ、水回りの配置などを決めます。
- 生活動線(家事動線、帰宅動線)がスムーズか、光や風の通り道は確保されているかなどを検討します。
- 後悔ポイント:「収納が足りなかった」「リビング階段にしたら音が響く」など、間取りの後悔は後から修正が困難です。
- 外観(デザイン、屋根の形、外壁材)
- 家の「顔」となるデザイン(シンプルモダン、ナチュラル、和モダンなど)を決めます。
- 屋根の形状(切妻、片流れなど)や外壁材(サイディング、タイル、塗り壁など)を選定します。
- 内部仕様(床材、壁紙、建具)
- 床材(無垢材、フローリング、タイルなど)、壁・天井の素材(壁紙、塗装、板張りなど)、室内ドアや窓枠(建具)の色やデザインを決めます。
- Point:部屋ごとではなく、家全体のトーン&マナーを統一させることが、洗練された空間づくりのコツです。
- 設備(キッチン、風呂、トイレ)
- キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレなどのメーカーやグレード、色を決定します。
- 食洗機の有無、浴室乾燥機の種類、造作洗面台にするかなど、細かな仕様も決めます。
- 電気・配線(コンセント、照明、スイッチ)
- 照明器具の種類と配置(ダウンライト、ペンダントライトなど)を決めます。
- コンセントやスイッチの位置と数を決定します。
- 後悔ポイント:「ここにコンセントがあれば便利だった」「スイッチの位置が生活動線と合わない」という後悔は非常に多いため、実際の生活をシミュレーションしながら決める必要があります。
2-4. 着工・完成フェーズ(約4〜6ヶ月)
設計図が完成し、いよいよ工事が始まります。このフェーズでも「決めること」は残っています。
- 着工後の各種確認
- 地鎮祭や上棟式を行うかどうかを決めます。
- 工事が設計図通りに進んでいるか、現場での確認(施主検査)を行います。
- Point:基礎工事や断熱材の施工など、完成すると見えなくなる部分こそ、信頼できる工務店にしっかり施工してもらうことが重要です。
- 外構(駐車場、フェンス、庭)
- 駐車場の台数と配置、門扉やフェンスのデザイン、庭や植栽の計画を決めます。
- Point:建物と外構はトータルでデザインすることが重要です。建物と同時に計画を進めると、予算配分もスムーズです。
- (場合によって)カーテン、家具の選定
- 窓のサイズに合わせてカーテンやブラインドを選定します。
- 新調する家具(ソファ、ダイニングテーブルなど)を決めます。間取りと同時に計画すると、サイズの失敗がありません。
横浜エリアで注文住宅を建てる際に特に注意して決めること
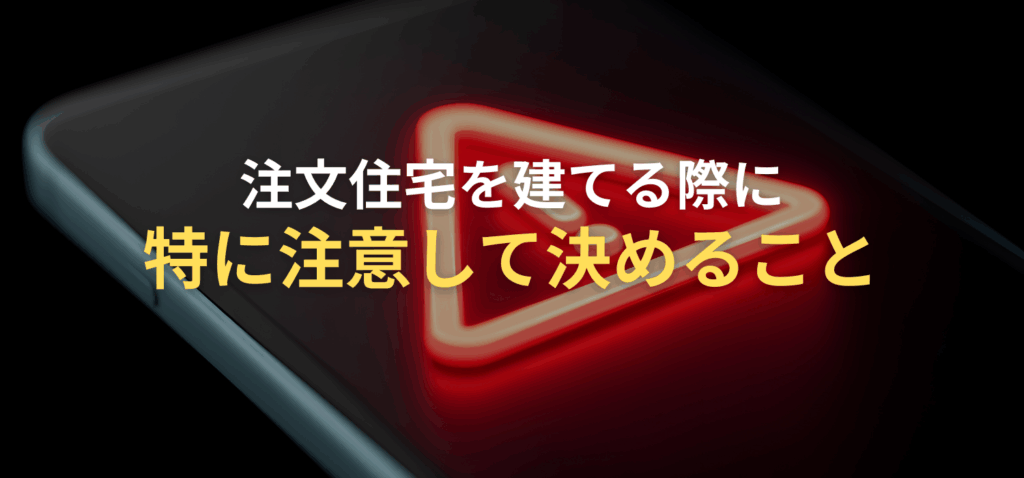
注文住宅で決めることは全国共通ですが、横浜・神奈川エリアには特有の地理的・法的な注意点があります。これらを知らずに計画を進めると、思わぬ失敗につながる可能性があります。
1. 坂道・高低差への対応(土地条件の確認)
横浜は坂が多い街です。高台の土地は眺望が良い反面、以下のような点を決める必要があります。
- 擁壁(ようへき)の要否
土地と道路に高低差がある場合、安全を確保するために擁壁の設置や補強が必要になるケースがあります。これは数百万円単位の追加費用がかかるため、土地決定前の最重要チェック項目です。 - 駐車スペースの確保
坂の途中の土地では、車の出し入れがしやすい駐車場の設計(ビルトインガレージなど)が求められます。 - アプローチの設計
玄関までの階段をどう設計するか、ベビーカーや将来の車椅子利用も考慮した動線を決める必要があります。
2. 敷地の特性(狭小地、防火地域など)に合わせた間取り
横浜市内や東京の城南エリアでは、土地の広さが限られる(狭小地)ケースも少なくありません。
- 3階建ての検討
敷地面積が限られる場合、容積率を最大限に活かす3階建てが有効な選択肢となります。 - 光と風の採り入れ方
隣家との距離が近い場合、吹き抜けや高窓(ハイサイドライト)を設けて、プライバシーを守りつつ光熱費を抑える設計を決める必要があります。 - 防火地域の確認
横浜駅周辺や主要な幹線道路沿いは「防火地域」や「準防火地域」に指定されていることが多く、使用できる窓や建材に制限がかかります。これをクリアしつつ、いかにデザイン性を高めるかが工務店の腕の見せ所です。
3. 横浜市の景観条例や建築ルールの確認
横浜市は、エリア(特に山手、みなとみらい周辺、歴史的建造物の周辺など)によって独自の景観条例を定めている場合があります。外観の色や素材、建物の高さなどに制限がかかることも。これらの法規制を熟知している、横浜の土地勘がある工務店を選ぶことが不可欠です。
▼横浜市の景観条例については
横浜市「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)」
「決めること」で後悔しないための優先順位の付け方
膨大な「決めること」を前に、後悔しないために最も重要なのは「優先順位」を明確にすることです。
「絶対に譲れないこと」と「妥協できること」を分ける
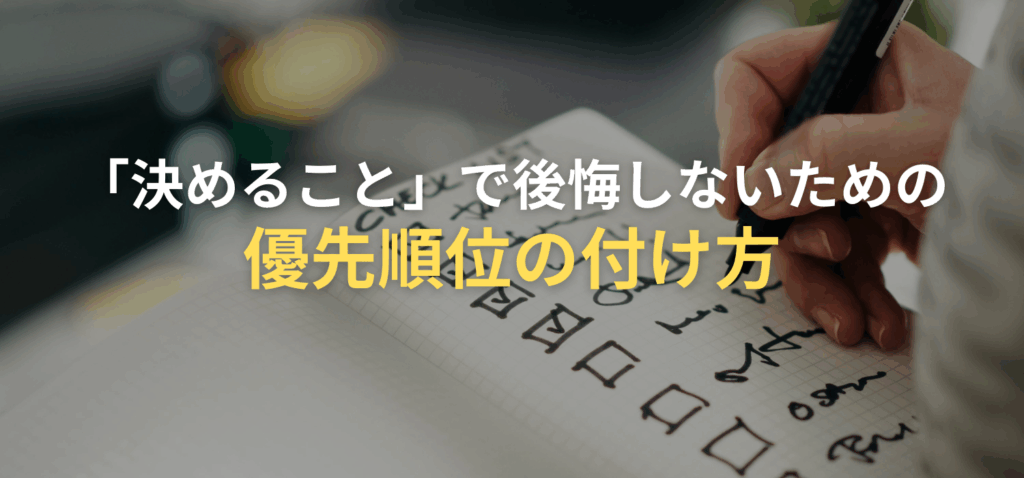
家づくりは予算との戦いでもあります。すべての希望を100%叶えようとすると、簡単に予算オーバーしてしまいます。
失敗しないためには、家族会議で以下の2つを明確に分けておくことが重要です。
- 絶対に譲れないこと(Must):
- 例:「耐震等級3は必須」
- 例:「家族の健康のための高断熱・高気密性能」
- 例:「通勤のための〇〇駅徒歩15分以内」
- できれば叶えたいが、妥協できること(Want):
- 例:「キッチンはA社が理想だが、性能が同等ならB社でも可」
- 例:「床材は無垢材が理想だが、リビングだけにして子供部屋はコストを抑える」
Point:家の基本性能(耐震、断熱)や、後から変更できない「土地」「間取りの根幹」は優先順位を高く設定し、設備や内装のグレードは調整可能な「Want」に分類するのがセオリーです。
予算オーバーを防ぐための「オプション」の決め方
打ち合わせでは、標準仕様から変更する「オプション」を決める場面が多々あります。一つひとつは少額でも、積み重なると大きな金額になります。
- 決める基準は「本当にそのオプションは、私たちの暮らしに必要か?」です。
- 「あったら便利そう」レベルのものは一度保留にし、「絶対に譲れないこと」の予算を確保した上で、余裕があれば採用する、というルールを決めましょう。
家族会議で意見が割れたときの対処法
「夫は書斎が欲しい」「妻はパントリーが必須」など、意見が割れることも当然あります。
- その際は、「なぜそれが必要なのか?」という背景(例:在宅ワークに集中したい、食材をストックして買い物の手間を減らしたい)を共有し合いましょう。
- 両方の希望を満たす代替案(例:リビングの一角にカウンターを設ける、キッチンの壁面収納を充実させる)を、プロ(設計士)に提案してもらうのが解決の近道です。
スムーズな打ち合わせのコツと「やることリスト」活用法
「決めること」が多い設計打ち合わせをスムーズに進めるには、事前の準備が鍵となります。
1. 事前に準備しておくこと
- 理想の写真(スクラップブック)
InstagramやPinterestなどで見つけた、好みの外観、内装、キッチンの写真をまとめておくと、設計士にイメージが正確に伝わります。 - 現在の住まいの「不満点リスト」
「収納が少ない」「コンセントが遠い」「冬が寒い」など、今の家の不満点を書き出すこと。これは、新しい家で「絶対に譲れないこと」そのものになります。 - 手持ちの家具リスト
新居に持っていく予定の家具(ソファ、ベッド、タンスなど)のサイズを測っておくと、間取り決めの際に役立ちます。
2. 打ち合わせの記録と確認の重要性
- 打ち合わせで「決めること」は、必ず議事録として書面に残してもらいましょう。
- 「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、決定事項と次回の宿題を双方で確認することが重要です。
- 膨大な決定事項を管理するために、本記事のような「やることリスト」やスケジュール表を活用し、今どの段階にいるのかを常に把握しておきましょう。
まとめ:決めることをリスト化して、横浜での理想の家づくりを成功させよう
横浜で注文住宅を建てる際に「決めること」は膨大ですが、恐れる必要はありません。
重要なのは、
- 家づくり全体の流れ(スケジュール)と順番を把握すること。
- 「構想」→「土地・会社」→「設計」→「着工」の各フェーズで決めることをリスト化し、一つずつクリアすること。
- ご家族にとっての「絶対に譲れないこと」という優先順位を持つこと。
です。
これらを明確にしておけば、打ち合わせは「大変な作業」ではなく、「理想を形にしていくワクワクする時間」に変わります。
ハビタットでは、横浜・神奈川エリアの土地特性を知り尽くしたプロが、あなたご家族だけの「決めることリスト」の整理から、家づくりのあらゆる不安に寄り添います。