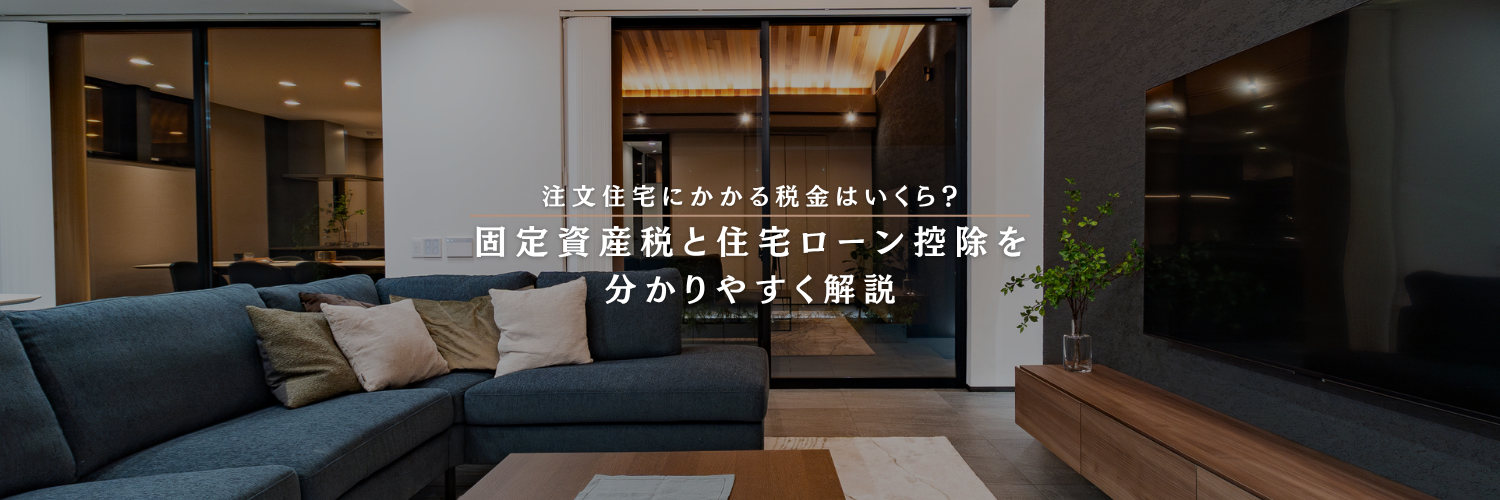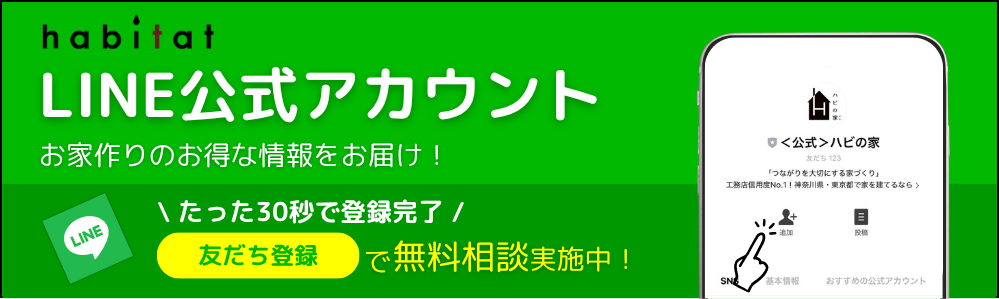はじめに:その「税金」の不安、私たちと一緒に解消しませんか?

横浜・神奈川・東京エリアで、こだわりの注文住宅をお考えのあなたへ。 理想の間取りやデザインに胸を膨ませる一方で、「家を建てた後、税金は一体いくらかかるのだろう?」「固定資産税って毎年払うって聞くけど、大丈夫かな…」「住宅ローン控除がお得だって聞くけど、手続きが複雑そう…」といった、お金にまつわる漠然とした不安を感じてはいませんか?
家づくりは、人生で最も大きな買い物の一つ。だからこそ、デザインや性能だけでなく、将来にわたって続く税金の知識を事前にしっかりと身につけ、賢い資金計画を立てることが、心から満足できる家づくりを実現する鍵となります。
この記事では、注文住宅を建てる際に「いつ」「どんな税金が」「いくらくらい」かかるのか、そして賢く節税するための「住宅ローン控除」や「固定資産税の軽減措置」といった重要な制度について、注文住宅を建てる視点から分かりやすく徹底解説します。
複雑で難しそうに感じる税金の話も、一つひとつ順を追って理解すれば、決して怖いものではありません。この記事を読み終える頃には、税金に対する不安が解消され、自信を持って家づくりの次のステップへ進めるようになっているはずです。
【ご確認ください】 本記事に掲載されている情報は、2025年10月時点の法令等に基づいています。税制は改正されることや、お客様の個別の状況によって適用条件が異なる場合がございます。必ず、管轄の税務署やお住まいの自治体の担当窓口にて最新の情報をご確認ください。なお、本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
【全体像】注文住宅の税金はいつ払う?家づくりのステップ別・税金のタイミング
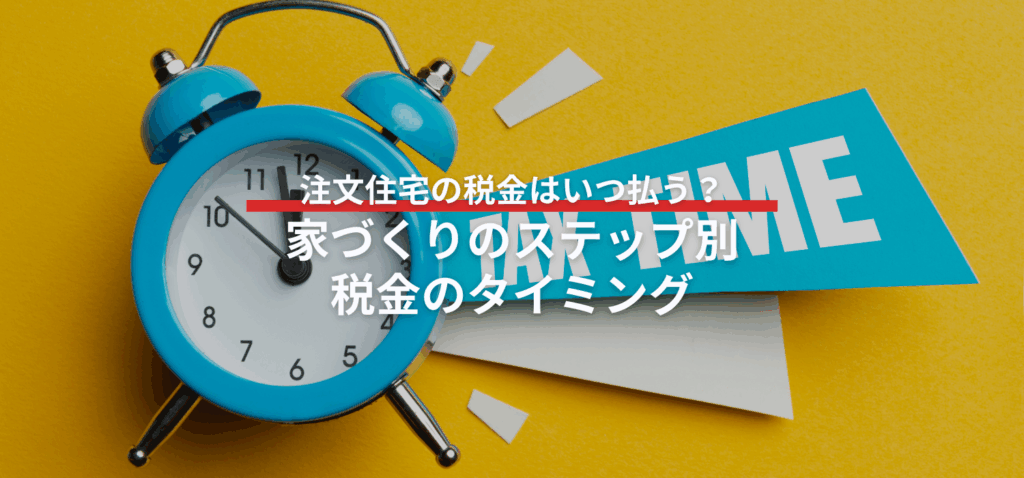
注文住宅の税金は、一度にまとめて支払うわけではなく、家づくりの各ステップで発生します。まずは、「土地の購入」から「建物の建築」、「入居後の暮らし」まで、どのタイミングでどんな税金がかかるのか、全体像を把握しましょう。
| 家づくりのステップ | 発生する主な税金 | 支払うタイミングの目安 |
| ① 土地・建物の契約時 | 印紙税 | 契約書を交わす時 |
| ② 不動産の登記時 | 登録免許税 | 土地・建物の所有権を登記する時 |
| ③ 不動産の取得時 | 不動産取得税 | 入居後、数ヶ月〜1年後 |
| ④ 不動産の所有中 | 固定資産税・都市計画税 | 毎年(入居した翌年から) |
| ⑤ 住宅ローン利用時 | 住宅ローン控除(所得税・住民税の減税) | 毎年(入居した翌年から最長13年間) |
| ⑥ 親などから資金援助 | 贈与税 | 資金援助を受けた翌年の申告期間 |
このように、税金には様々な種類があり、支払うタイミングも異なります。特に重要なのが、毎年支払いが発生する「固定資産税」と、賢く活用したい「住宅ローン控除」です。次章から、それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
【タイミング別】注文住宅にかかる主要な税金4種

それでは、具体的にそれぞれの税金がどのようなもので、いくらくらいかかるのかを解説します。
1. 契約時にかかる「印紙税」
土地の売買契約書や、建物の建築工事請負契約書といった「契約書」に対して課される税金です。契約書に記載された金額に応じて、収入印紙を貼り付けて納税します。
- 軽減税率の目安:
- 契約金額が1,000万円超 5,000万円以下の場合:1万円
- 契約金額が5,000万円超 1億円以下の場合:3万円 ※不動産売買契約書等について、2027年3月31日までに作成されるものには軽減措置が適用されます。
出典:国税庁 「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
2. 登記時にかかる「登録免許税」
購入した土地や完成した建物が「誰のものか」を法的に証明するため、法務局に所有権を登録(登記)する際にかかる税金です。
税額は、不動産の評価額である「課税標準額(固定資産税評価額)」に、定められた税率を掛けて計算します。
- 計算式: 課税標準額 × 税率
- 税率の目安:
- 土地の所有権移転登記:1.5%(通常2.0%から軽減措置適用。)
- 建物の所有権保存登記(新築):0.15%(通常0.4%から軽減措置適用。) ※軽減措置の適用には、床面積50㎡以上など一定の要件があります。
※語句の説明
課税標準額:課税におけて、課税金額算出する上で基礎となる金額のこと
3. 取得時に一度だけかかる「不動産取得税」
土地や建物を取得したことに対して、一度だけ課される都道府県税です。忘れた頃(入居から数ヶ月~1年後)に納税通知書が届くため、慌てないように準備しておくことが大切です。
- 計算式: (課税標準額 – 控除額) × 税率
- 税率: 3%(通常4%から軽減措置適用)
【重要ポイント】新築住宅には大幅な軽減措置があります。 新築の注文住宅の場合、建物の課税標準額から1,200万円が控除されます。この控除額が非常に大きいため、多くの新築住宅では不動産取得税が大幅に減額されます。軽減措置を受けるためには、お住まいの都道府県税事務所への申告が必要です。
出典: 国土交通省「不動産取得税に係る特例処置」
※本記事の内容は、執筆時点の法令や制度をもとに作成しています。実際の税額や軽減措置の適用可否については、各自治体や税務署にご確認ください。弊社では税額の算定や軽減措置の適用結果について責任を負いかねます。
4. 【最重要】所有している間ずっとかかる「固定資産税・都市計画税」
注文住宅を建てた後、最も長く付き合っていくことになるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。毎年1月1日、固定資産の所有者に対して課税され、年に4回に分けて(または一括で)納税します。
注文住宅の固定資産税は「いつから」払う?
固定資産税は、家が完成した翌年から支払いが始まります。例えば、2025年10月に家が完成した場合、2026年度から課税対象となり、2026年の春頃に最初の納税通知書が届きます。
固定資産税は「いくら」かかる?計算方法とシミュレーション
固定資産税の額は、自治体が算出する「固定資産税評価額」を基に計算されます。新築の場合、この評価額は建築費のおおよそ50%~70%が目安となります。
- 計算式:
- 固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税 = 課税標準額 × 最高0.3%(※市街化区域内の場合)
【横浜市で注文住宅を建てた場合のシミュレーション】
土地:1,500万円(評価額)
建物:2,000万円(評価額)、新築、長期優良住宅
税率:固定資産税 1.4%、都市計画税 0.3%
▼土地のシミュレーション例
・固定資産税:1,500万円 × 1/6 (住宅用地の特例) × 1.4% = 35,000円
・都市計画税:1,500万円 × 1/3 (住宅用地の特例) × 0.3% = 15,000円
土地の合計:約50,000円
▼建物のシミュレーション例
・固定資産税:2,000万円 × 1/2 (新築住宅の減額) × 1.4% = 140,000円
建物の合計:約140,000円
年間の固定資産税・都市計画税の合計:約190,000円
【重要ポイント】新築住宅は固定資産税が3年間(長期優良住宅は5年間)1/2に減額されます。 シミュレーションの通り、新築住宅には大きな軽減措置が用意されています。しかし、この期間が終了すると税額は本来の額に戻るため、資金計画にはその点も織り込んでおく必要があります。
出典:総務省「固定資産税」
【賢く節税】注文住宅で絶対に見逃せない2大優遇制度

ここまでは支払う税金について解説してきましたが、課税の対象となる所得額を減らし、税制上の範囲内で税負担を軽減する「節税」に繋がる重要な制度をご紹介します。これらを活用するかどうかで、総支払額に大きな差が生まれます。
1. 最も影響が大きい「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%が、所得税(引ききれない場合は一部住民税)から最大13年間控除されるという、非常に強力な節税制度です。
住宅ローン控除は「いつから」受けられる?
住宅ローン控除は、入居した年の翌年から受けることができます。初年度はご自身で確定申告を行う必要がありますが、会社員の方であれば2年目以降は年末調整で手続きが完了します。
控除額はいくら?住宅の性能で上限が変わる
住宅ローン控除で戻ってくる金額は、住宅ローンの年末残高と、取得する住宅の省エネ性能によって決まる「借入限度額」によって上限が定められています。
【2024・2025年入居の場合の借入限度額】
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額(年間) |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 |
| その他の住宅 | 0円 ※ | 0円 |
※2024年以降に建築確認を受ける「その他の住宅」は原則として住宅ローン控除の対象外となります。
このように、建てる家の性能が、将来の節税額に直接影響します。 ハビタットでは、デザイン性はもちろん、長期優良住宅やZEH水準の高い省エネ性能を持つ住まいを標準仕様としてご提案し、お客様の長期的なメリットを追求しています。
出典:国土交通省「住宅ローン減税」
2. 親からの資金援助を考えているなら「贈与税の非課税措置」
親や祖父母から住宅取得のための資金援助を受ける場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。(適用期限は、2026年12月31日まで)
- 非課税限度額:
- 省エネ等住宅: 1,000万円
- 上記以外の住宅: 500万円
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この特例を使えば、まとまった資金を非課税で受け取ることができ、自己資金を厚くすることが可能になります。適用には一定の要件があり、贈与を受けた翌年に申告が必要です。
出典:国税庁 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
まとめ:複雑な税金と資金計画は、信頼できるパートナーと共に
今回は、注文住宅に関わる税金について、支払うタイミングから具体的な計算方法、そして賢い節税制度までを網羅的に解説しました。
- 家づくりの各段階で、印紙税、登録免許税、不動産取得税などが発生する。
- 入居翌年から、毎年「固定資産税」の支払いが発生するが、新築には大きな軽減措置がある。
- 「住宅ローン控除」は最大の節税策。省エネ性能の高い家ほど控除額が大きくなる。
- 親からの資金援助には「贈与税の非課税措置」を活用できる。
税金の話は複雑で、一人ですべてを完璧に理解し、最適な選択をするのは簡単なことではありません。特に、どの優遇制度が自分たちに適用できるのか、そのためにはどんな性能の家を建てるべきなのか、といった判断には多くの情報収集が不可欠です。
だからこそ、私たちハビタットのような、お客様の家づくりに真摯に向き合うパートナーを選ぶことが重要になります。私たちは、横浜・神奈川・東京エリアでの豊富な建築実績に基づき、お客様一組ひと組のライフプランに合わせた最適な資金計画をご提案します。デザインや間取りのご相談はもちろん、複雑な税金や補助金の活用方法まで、トータルでサポートさせていただきます。
※本記事でご紹介した内容は、あくまで資金計画の参考としてご活用いただき、税に関する最終的な判断や手続きについては、必ず管轄の税務署や自治体にご確認いただきますようお願いいたします。なお、本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
家づくりは、信頼できるパートナーとの出会いから始まります。まずは一度、あなたの理想の住まいについて、そして資金計画に関する不安について、私たちにお聞かせいただけませんか?
ハビタットが手掛けた「特別な住まい」のデザインや、
具体的な価格帯が分かる最新のカタログをご用意しました。
まずは資料請求で、理想の家づくりのイメージを膨ませてみませんか?
▼▼ 無料で「ハビの家」のカタログを請求する ▼▼
参考元
- 国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) 」
- 総務省「固定資産税 」
- 東京都主税局:「不動産取得税」